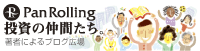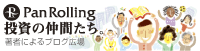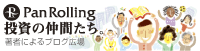
優利加の「生涯現役のトレード日記」
「知識社会」へ急速なパラダイムシフトが起こっている
07月18日
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +229.71 @44,484.49, NASDAQ +155.16 @20,885.65, S&P500 +33.66 @6,297.36)。ドル円為替レートは148円台後半での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が543に対して、下落銘柄数は1,037となった。騰落レシオは120.0%。東証プライムの売買代金は4兆45億円。
TOPIX -5 @2,834
日経平均 -82円 @39,819円
米国では、新規失業保険申請件数(22.1万件<予想23.5万件、先週発表分22.8万件)も6月小売売上高(前月比+0.6%>予想+0.1%)も強く、景気減速懸念が和らいでいる。週間ベースの新規失業保険申請件数は5週連続で下げている。高関税の悪影響は今のところほとんど出ていないようである(時間が経過すれば、必ず悪影響は出てくるが)。台湾積滞電路製造(TSMC)が好決算を発表して株価が大きく上昇した。S&P500もナスダックも取引時間中の史上最高値を更新した。終値ではS&P500が今年9回目の史上最高値を更新し、ナスダックは10回目の史上最高値更新を記録した。
それにしてもエヌビディアの成長ぶりには驚かされるばかりである。7月9日には上場企業としては史上初の時価総額4兆ドル(約600兆円≒日本の名目GDP)を突破した。この1銘柄だけでS&P500の約8%を占める。マイクロソフトも3.8兆ドルまで時価総額を増やしており、「4兆ドルクラブ」の仲間入り目前である。どうしてこのような大きな変化が起こっているのだろうか。革命的なパラダイムシフトが起こっているからである。20世紀の終わり頃までは、企業の収益の源泉は巨大なもの作りのための機械や装置・工場などの「有形固定資産」だった。しかし、2000年頃から企業の収益の源泉は人間の頭脳・知恵が直接生み出すもの、つまり「貸借対照表には表れない無形固定資産」にシフトし始め、今や世界経済は明確な「知識社会」へ急速に変貌しており、それを端的に物語るのがGAFAMの時価総額である。この大きな変化に上手に反応しているアマゾン・ドットコムやマイクロソフトのようなハイパー・スケーラー(大規模クラウド事業者)が10〜30年先を見越してAIの開発・実装に不可欠のデータセンター関連施設に巨額の資金を投じている。その巨額投資のかなりの部分を占めるAI半導体をほぼ独占的に供給しているのがエヌビディアであり、その高い成長性の持続が予想PER34倍でも割高と思わせないのである。
本日7月18日の東京市場では、米ハイテク株は足元で上昇してきたが、明日からの3連休を控えて、さらに20日の参院選の結果が気になり、持ち高整理や利益確定売りが優勢となった。アドバンテストが上昇が目立っていたが、利益確定の売りに押された。前日に決算発表したディスコ(17日時点で予想PER52倍)は業績見通しが不透明といういうことで、大きく売られた。他方、ソフトバンク・グループが運用する投資ファンドは米ハイテク株に多額の投資しているため、ソフトバンク・グループ株は買われた。良品計画、イオン、高屋島やなど消費関連銘柄の一角は買われた。
日経平均の日足チャートを見ると、始値は4万円台を回復して高く始まったが、売りに押されて陰線で終えた。結局、7月2日から続いている横ばいレンジ相場内に終値では押し戻された。20日の参院選の結果によっては横ばいレンジ相場から放れるか。
33業種中22業種が下げた。下落率トップ5は、不動産(1位)、空運(2位)、パルプ・紙(3位)、鉄鋼(4位)、小売り(5位)となった。
ほぼ水平の10日移動平均の上に再浮上したが・・・
07月18日
昨日の米国株式相場は上昇した(DJIA +231.49 @44,254.78, NASDAQ +52.69 @20,730.49, S&P500 +19.94 @6,263.70)。ドル円為替レートは148円台後半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,172に対して、下落銘柄数は374となった。騰落レシオは117.41%。東証プライムの売買代金は4兆981億円。
TOPIX +20 @2,840
日経平均 +238円 @39,901円
米国では、6月生産者物価指数(PPI)が前年比+2.3%(<予想+2.5%、前月+2.7%)と伸びが鈍化し、利下げ期待が高まった。米10年債利回りは前日の4.489%から4.459%に低下し、主要3株価指数は揃って上昇した。
本日7月17日の東京市場では、20日に投開票する参院選を巡る不透明感、米国との関税交渉が難航していること、オランダ半導体装置大手ASLMが業績見通しについて先行き慎重な姿勢を示したことなどから、本日の日本株全般は売り先行で始まり、前場では日経平均の下げ幅は一時300円近くまで拡大した。東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテックの3銘柄だけで、日経平均を約100円押し下げた。しかし、台湾積滞電路製造(TSMC)が日本時間の午後発表した2025年4〜6月期決算が良好だったことに反応して、下げて始まっていたディスコが買い戻されて上昇に転じ、東京エレクトロンやアドバンテストも急速に下げ幅を縮小した。日経平均は大引けにかけて急速に上げ幅を拡大した。カナダのアリマンタション・クシュタール(ACT)が買収提案(7兆円規模)を撤回したため、セブン&アイ株は急落した。
日経平均の日足チャートを見ると、下げて始まったが切り返して陽線で終え、ほぼ水平となっている10日移動平均の上に明確に再浮上した。しかし、まだ方向感がない。
33業種中26業種が上げた。上昇率トップ5は、その他製品(1位)、サービス(2位)、医薬品(3位)、情報・通信(4位)、保険(5位)となった。
無題
07月17日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -436.36 @44,023.29, NASADAQ +37.47 @20,677.80, S&P500 -24.80 @6,243.76)。ドル円為替レートは148円台後半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が568に対して、下落銘柄数は994となった。騰落レシオは110.27%。東証プライムの売買代金は4兆3945億円。
TOPIX -6 @2,819
日経平均 -15円 @39,663円
米国では、エヌビディアが低価格ブラックウェルAI半導体「H20」の中国向け輸出を再開するとの発表したことを好感して、エヌビディア株は4%超上昇してハイテク株の上昇をけん引した。しかし、6月米消費者物価指数(CPI)はほぼ市場予想と一致した(前月比+0.3%=予想+0.3%>5月+0.1%) が、その水準は4か月ぶりの高水準だった。EUとメキシコに新たに課す関税により、物価にはさらに上昇圧力がかかると予想され、米連邦公開市場委員会(FRB)は早期追加利下げをしにくくなる。この見立てを反映して、米10年債利回りは前日の4.427%から4.485%へ上昇した。大手金融機関の決算は好悪まちまちで、好決算を発表したシティー・グループは3.68%高となった一方、決算が悪かったウェルズ・ファーゴは5.48%安となった。純収入が市場予想を下回ったブラックロックも売られて5.88%安となった。
本日7月16日の東京市場では、米国市場で生成AI半導体製造のエヌビディアをはじめとしてハイテク株が買われたことを好感して、東京エレクトロン、アドバンテスト、フジクラなどが上げて、株価指数を下支えした。米長期金利の上昇を反映して、1ドル=149円台まで円安ドル高が進行したことも手伝い、日経平均の上げ幅は200円を超える場面があった。しかし、オランダ半導体製造装置大手のASLMホールディングの決算発表で、先行きが不透明すぎるせいか2026年度の見通しを示さなかったため、関連株の値動きが荒くなった。米国市場では大手銀行株が決算発表を受けて売られる銘柄が多かった。その流れで、東京市場でも銀行株や保険株は売り優勢となった。また、20日に投開票が行われる参院選では、与党である自民・公明の両党の苦戦が世論調査結果として報じられると、海外短期筋が売りを仕掛けて、日経平均は一時150円超まで下げた。
日経平均の日足チャートを見ると、上昇したが上下にひげを引いた短陰線で終え、ほぼ水平の10日移動平均線と同じ水準で終値となった。7月2日以来続く横ばいレンジ内の動きであり、依然として方向感がない。
33業種中25業種が下げた。下落率トップ5は、不動産(1位)、パルプ・紙(2位)、証券(3位)、銀行(4位)、保険(5位)となった。
国内長期金利の上昇が顕著になって来たので・・・
07月16日
昨日の米国株式相場は小幅上昇した(DJIA +88.14 @44,459.65, NASDAQ +54.80 @20,640.33, S&P500 +8.81 @6,268.56)。ドル円為替レートは147円台後半での推移だった。本日の日本株全般は下げる銘柄の方がやや多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が626に対して、下落銘柄数は932となった。騰落レシオは116.92%。東証プライムの売買代金は4兆1219億円。
TOPIX +3 @2,825
日経平均 +218円 @39,678円
米国では、トランプ大統領が週末に欧州連合(EU)とメキシコからの輸入品に対し、8月1日から30%の関税を課すと発表したが、マーケットは額面通り受け止めてはいない。いずれ交渉により実際の関税は下がると見ている。いつものトランプ大統領の常套手段で、最初は高い数字で脅かしておき、その後の交渉を有利に運ぼうというスタイルであるとマーケットは見抜いているようだ。
トランプ大統領は14日、ロシアに対して50日以内にウクライナと停戦しなければ「非常に厳しい関税を課す」と表明した。具体的には、ロシアから石油などを購入した国に100%の「二次関税」を課す。しかし、これもまたは単なる交渉手段であるとマーケットは受け止めており、今のところ、それほどの悪材料とは解釈していない。
本日7月15日の東京市場では、米エヌビディアが中国向けに開発した人工知能(AI)半導体「H20」の輸出再開を表明したことを受けて、東京エレクトロンやアドバンテストなど日本の半導体関連銘柄に買いが入った。東証プライムでは上昇銘柄数の方が少なかったが、値嵩株が上昇したことで株価指数の算出の仕組み上(株価の単純平均)、日経平均も上昇した。ただ、日本時間の今夜発表される6月米消費者物価指数(CPI)の結果が気になり、様子見ムードが強かった。なぜなら、米CPIの上昇率が事前予想よりも強いと、米連邦準備制度理事会(FRB)による追加利下げ観測が後退して、米株価が下がる可能性が高まるからである。
国内債券市場では、長期金利の指標である新発10年債利回りが一時1.595%まで上昇した。これは2008年10月以来、約17年ぶりの高水準であった。この国内長期金利の上昇を受けて、メガバンクをはじめとする銀行株や第一生命や東京海上などの保険株などが上げた。三菱UFJをはじめとするメガバンクだけでなく、七十七銀行や武蔵野銀行など地銀株の一角も上げた。他方、借入残高が大きいため金利上昇により金利負担が大きくなる不動産株や鉄道株は軟調だった。長期金利上昇の背景には、7月20日の参院選後に財政拡張的な政策(給付金バラマキ、消費税減税:財政悪化が進むことを意味する)が行われるとの見通しが強くなる中、米長期金利の上昇に引きずられて国内長期金利も上昇した。財政リスクを反映しやすい超長期債も売られて、新発30年債利回りは一時3.200%まで上昇し、発行開始以来の最高値を更新した。20年債利回りも一時2.650%まで上昇して、1999年11月以来の高水準を記録した。
超長期債は買い手が不在のため、少しの売りで利回り(金利)が上げやすい。ということは安易に超長期債を買うと、すぐに含み損が拡大することを意味する。したがって、金利が上がりそうな局面では、長期債を売り、より満期が短い債券に乗り換えることが合理的な行動となる。その結果、イールドカーブは短期が下げ、長期が上がることになり、傾きがより急(スティープ)になる。足元の長期金利上昇は、日銀の利上げ観測が高まったからではなく、債券の需給要因と財政悪化によるリスク・プレミアムの高まりにより起こっている。
日経平均の日足チャートを見ると、7月11日から下向きに転じた10日移動平均線の下で株価は依然として推移しているが、本日は陽線で小幅反発した。それでも7月2日以来継続している横ばいレンジ相場内での変動である。
33業種中14業種が上げた。上昇率トップ5は、非鉄金属(1位)、保険(2位)、電気機器(3位)、医薬品(4位)、電気・ガス(5位)となった。
トランプ政権の関税率引き上げは「交渉術」と受け止めてられてはいるが・・・
07月14日
先週金曜日の米国株式相場は反落した(DJIA -179.13 @44,371.51, NASDAQ -45.14 @20,585.53, S&P500 -20.71 @6,259.75)。ドル円為替レートは147円台前半の先週末比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄の方がやや多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が907に対して、下落銘柄数は649となった。騰落レシオは117.54%。東証プライムの売買代金は3兆6610億円。
TOPIX ±0 @2,823
日経平均 -110円 @39,460円
米国では、前日の引け後にトランプ米大統領がカナダからの輸入品に対して35%の関税を8月1日から課すと表明した。さらに11日までに欧州連合(EU)にも新税率を通知する考えを示した。物価上昇懸念を反映して、米長期金利(10年債利回り)は前日の4.35%台から4.4%台前半へ上昇した。貿易摩擦が景気を減速させ、物価を上昇させるという懸念がまた改めて意識された。S&P500とナスダックは前日に史上最高値を更新するほど上げてきたので、短期的な過熱感や高値警戒感も出ている中で、高値圏にある主力株に利益確定の売りが優勢となった。トランプ政権の関税率の引き上げは「交渉術」であると投資家は受け止めているが、それでも反応せざるを得ない。人口知能(AI)関連の収益増加が期待されるエヌビディアやアマゾンは引き続き買いが優勢で株価は上昇した。次週は、大手銀行をはじめとする主要企業の決算発表が本格的に始まる。さらに、6月米消費者物価指数(CPI)、6月米小売売上高など注目を集める経済統計指標が発表されるため、投資家全体として売買にやや慎重になった。
米国は12日に、欧州連合(EU)とメキシコに対して8月1日から30%の関税を課すと表明した。本日7月14日の東京市場では、米関税政策の先行き不安が続く中、20日の参院選投開票を巡る不透明感から、与党が過半数割れすると賭けた一部海外投機筋が先物で売りを仕掛けて、日経平均の下げ幅は一時300円を超えた。他方、米長期金利の上昇を反映して、円安ドル高が進行して1ドル=147円台前半となり、トヨタ自動車やホンダなどの自動車や、第一三共、アステラス製薬、中外製薬など医薬品が買われて株式相場を下支えした。三菱重工や日本製鋼などの防衛関連銘柄も上げた。米関税政策による景気悪化懸念により日銀の早期利上げは遠のき、期待されてきた利ザヤ改善もお預けとなり三菱UFJをはじめとするメガバンク株は下げた。
日経平均の日足チャートを見ると、7月2日以来続いてきた横ばいレンジ相場の下限を下へ突き破りそうな水準まで下げた。
33業種中19業種が上げた。上昇率トップ5は、電気・ガス(1位)、機械(2位)、不動産(3位)、輸送用機器(4位)、保険(5位)となった。
「幻のSQ」、上値抵抗線として意識されやすい
07月12日
昨日の米国株式相場は上昇した(DJIA +192.34 @44,650.64, NASDAQ +19.33 @20,630.67, S&P500 +17.20 @6,280.46)。ドル円為替レートは146円台後半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,152に対して、下落銘柄数は420となった。騰落レシオは116.45%。東証プライムの売買代金は4兆5653億円。
TOPIX +11 @2,823
日経平均 -77円 @39,570円
米国では、新規失業保険申請件数が22.7万件(<予想23.5万件、先週発表分23.3万件)と減少したことで、労働市場減速への警戒感が和らいだ。前週に発表された6月米雇用統計も予想以上に好調だった。米景気の底堅さが航空会社の決算でも確認された。デルタ航空の第2四半期(4~6月)決算が売り上げも利益も事前予想を上回り、第3四半期の業績見通しも予想を上回ったことで、株価は11.9%上昇した。これに触発されて、ユナイテッド航空も14%上げ、サウス・ウェスト航空も8.14%上げ、ノルウェー・クルーズ・ラインも5.42%上げた。旅行・レジャー銘柄が軒並み上げた。これまでハイテク株に遅れ気味だった、消費関連株や景気敏感株も買われた。トランプ減税の恒久化を含む減税・歳出法が成立し、関税政策への過度な警戒感が薄れており、旅行需要が回復している。S&P500とナスダックはともに史上最高値を更新した。
米トランプ政権は銅・銅製品への50%の関税を8月1日に発動する方針を示しており、ブラジルに対しては相互関税を50%にする(米国は対ブラジルで貿易黒字にもかかわらず!)と表明した。世界各国に対して狂気の高関税策で脅しながら自国に有利なディール(取引)をしようとしているが、TACO(Tramp Always Chikens Out)なので最終的には許容範囲内の税率に落ち着くだろうとマーケットは判断しているようである。もし、報復関税の連鎖により世界中をブロック経済圏に分断して最終的に第2次世界大戦へとつながった1930年のスムート・ホーリー関税法(約20,000品目の輸入品に平均60%の高関税を課した)に匹敵するかそれ以上の高関税が数年も続けば、米国も世界も悲惨な結果を見ることになる。ある程度の歴史と経済学の教養がある人なら容易に想像できるのだが。しかし、トランプ大統領は、永久磁石は水につかると磁力を失うと公言しするほどの「教養」の持ち主である。また、つい最近、リベリアの大統領が国際会議できれいな英語で演説をすると、驚いて「英語はどこで学んだのか」と尋ねるほどの「素晴らしい教養」の持ち主なので、楽観は禁物だろう。リベリアは、南北戦争後、米国で奴隷の身分から解放された黒人が西アフリカに建国した国で、公用語は英語、通貨はリベリア・ドル、アフリカでは一度も植民地支配されなかったエチオピアに次ぐ古い国である。
本日7月11日の東京市場では、米国株高を受けて高く始まったが、節目の4万円に接近すると売りが増えて頭を抑えられた。それでもレーザーテック、ディスコ、アドバンテストなど半導体関連銘柄が買われた。ただ、前日に決算発表をしたファーストリテイリングが急落して1銘柄だけで日経平均を262円押し下げた。トランプ大統領は8月1日からカナダからの輸入品に35%の関税を課すと10日に表明し、トランプ政権の高関税政策の着地点が未だに見えないため、日本経済に対する負荷も予想が難しい。また、20日に投開票される参院選で与党の自民・公明党がどれだけの議席数を確保できるか次第で、政権の安定度が左右されるので、これも気になる。
本日は株価指数オプション7月物の特別清算指数(SQ)が算出される日だった。SQ値は構成銘柄の始値で算出するが、実際に寄り付かなくても5秒ごとに気配値でも算出される。したがって、仕組み上、寄付きでは気配値だけでなかなか寄り付かず、実際の始値が遅れる日経平均構成銘柄数が多いほど、SQ値と日経平均の高値との乖離が大きくなる。本日のSQ値は前日比358円高の40,004円61銭だった。SQ値が日経平均の高値を上回る場合、「幻のSQ」と呼び、その後の上値抵抗線として意識される。本日の「幻のSQ」の主因はファーストリテイリングの急落だった。10日に発表した2024年9月〜2025年5月期の連結決算は営業利益が前年同期比12%増の4,509億円となり、この期間としては史上最高益だった。しかし、株式市場はそれ以上の結果を期待していたため、失望売りが寄り付き前から殺到して、株価は一時7%安となった。
海外投資家は7月第1週(6月30〜7月4日)に日本株を5,456億円買い越し、これで14週連続の買い越し記録となった。アベノミクス相場開始の時期である2012年11月〜2013年3月(18週連続)以来、約12年ぶりの長期記録となった。当時は、アベノミクス政策によるリフレ政策や2023年春には東証がPBRの改善を上場企業に求めるなどの明確な相場背景・理由があった。それとは対照的に、現在の外国人投資家による買い越し記録はこれといった理由がなく、強いて挙げれば、欧米や新興国で株高となっているから「連れ高」しているということだろう。つまり、日本独自の理由はないということである。その結果、1年前の2024年7月11日に日経平均は42,224円を付けたが、その後は高値を更新できずにいる。これに対して、この間、欧米や新興国の一部では株価は史上最高値を更新した。この1年間、日本株で際立った上昇をしたのは防衛関連銘柄、電線銘柄、ゲーム関連銘柄など明確な株価材料があった銘柄だった。逆に米国の高関税政策という悪材料があった自動車関連銘柄や中国関連銘柄は目立って下げた。
日経平均の日足チャートを見ると、高く始まったが売りに押し返されて陰線で終えた。7月2日以来の横ばい相場の基調は変わらない。
33業種中25業種が上げた。上昇率トップ5は、海運(1位)、鉄鋼(2位)、パルプ・紙(3位)、証券(4位)、銀行(5位)となった。
「株価の原理原則」でTOPIXとS&P500を「因数分解」して比べてみると・・・
07月11日
昨日の米国株式相場は上げた(DJIA+217.54 @44,458.30, NASDAQ +192.87 @20,611.34, S&P500 +37.74 @6,264.26)。ドル円為替レートは145円台後半から146円台前半での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が522に対して、下落銘柄数は1,040となった。騰落レシオは113.02%。東証プライムの売買代金は4兆7734億円。
TOPIX -16 @2,812
日経平均 -175円 @39,646円
米国では、米長期債の利回りが低下した(前日の4.417%から4.335%へ)ことを好感して株価は上げた。生成AI普及による好業績の継続を期待してエヌビディアなどのAI関連銘柄を中心に上げた。エヌビディアは一時、時価総額が4兆ドル(約590兆円>日本の名目GDP550兆円!!!)台(史上初)まで上昇した。マイクロソフトも高値を更新し、アマゾンも上昇した。主要3株価指数は揃って上昇した。
本日7月10日の東京市場では、ソフトバンク・グループやディスコなど上昇する銘柄もあり、特にアドバンテストが上場来高値を更新した。しかし、米長期金利の低下を反映して円高ドル安が進んだことで輸出関連銘柄が売られた。また、大引けでは上場投信(ETF)の分配金捻出目的の売りが出ることが予め分かっていたので、先回りしてザラバで株価指数先物などで売りが出たと見られる。
株価の原理原則の一丁目一番地は「株価P=予想PER X予想EPS 」である。この原理原則に照らし合わせて年初から株価の動きを考える。東証株価指数(TOPIX)の上昇を分解すると、予想PERが9%上昇した一方、予想EPSは逆に3%下落した。つまり、両者のベクトルの方向が反対であり、期待だけで上昇している。では、米国株のベンチマークであるS&P500はどうなっているか。予想PERが10%上昇しているのに対して、予想EPSは2%の上昇であり、ベクトルの方向はおちらもプラスで一致している。株価はいつまでも上がり続けることはなく、必ずどこかのタイミングで反落し始める。日米どちらが先に「ガス欠」になるかと考えると、おそらく日本株だろうというのが合理的な予想である。但し、それがいつになるかは明確に事前に知ることは不可能ではあるが。外国人投資家の長期目的の買いが継続している(外国人投資家は4月第1週から14週連続の買い越し、その累積買い越し額は4.9兆円)ので、当面は大崩れはなさそうである。米トランプ大統領が1月に就任して以来、米国市場偏重を修正するために、投資金が米国からまず欧州へ、次に中国へ、そして出遅れ感が強かった日本へとシフトして来た。
日経平均の日足チャートを見ると、下ひげを引いた陰線で小幅反落した。7月2日から続いている横場レンジの真ん中くらいにまた戻った。
33業種中26業種が下げた。下落率トップ5は、電気・ガス(1位)、その他製品(2位)、石油・石炭(3位)、海運(4位)、鉱業(5位)となった。
小幅高となったが依然として横ばい相場が継続中
07月09日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -165.60 @44,240.76, NASDAQ +5.95 @20,418.46, S&P500 -4.46 @6,225.52)。ドル円為替レートは146円台後半の前日比円安ドル高水準での動きだった。
本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,259に対して、下落銘柄数は315となった。騰落レシオは113.54%。東証プライムの売買代金は4兆2947億円。
TOPIX +12 @2,826
日経平均 +132円 @39,821円
米国では、インテルやエヌビディアなどの半導体銘柄は上昇したが、HSBCが投資判断を引き下げたJPモルガンチェースやバンク・オブ・アメリカなど大手金融機関銘柄は下落した。トランプ米大統領は、各国に通知した新税率は8月1日から発動するとし、延長は認められないとした。銅・銅製品の輸入には50%、医薬品には最大200%の輸入関税を課すとも言っている。
本日7月9日の東京市場では、外為市場で円安ドル高が進行したことを受けて自動車株などの輸出関連銘柄が買われたのに加えて、米ハイテク株の上昇を受けて、東京エレクトロンやアドバンテストなどの値がさ半導体銘柄も買われた。日経平均の上げ幅は一時280円を超えた。
日経平均の日足チャートを見ると、下ひげを引いた短陰線で小幅高となった。7月2日から4万円が上値抵抗線となる横ばい相場が継続している。
33業種中27業種が上げた。上昇率トップ5は、石油・石炭(1位)、鉱業(2位)、その他金融(3位)、証券(4位)、精密機器(5位)となった。
25%の関税率は想定の範囲内だったので・・・
07月08日
昨日の米国株式相場は大きく反落した(DJIA -422.17 @44,406.36, NASDAQ -188.59 @20,412.52, S&P500 -49.37 @6,229.98)。ドル円為替レートは146円台前半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,083に対して、下落銘柄数は484となった。騰落レシオは110.88%。東証プライムの売買代金は4兆5433億円。
TOPIX +5 @2,817
日経平均 +101円 @39,689円
米国では、トランプ米大統領が8月1日から日本と韓国に25%の関税を課すと表明し、ブラジル、ロシア、インド、中国などのBRICS諸国に対しては10%の追加関税を課す可能性も示した。これが世界景気を冷やすとの懸念から米国株全般は売り優勢となった。ダウ工業株30種平均は一時668ドルまで下げた。
本日7月8日の東京市場では、トランプ米大統領が表明した25%の関税は先週ほのめかしていた30〜35%より低かったことで、25%という数字は想定の範囲内と受け止められた。25%の関税だが実施は8月1日とうことは実質的な「延長」であり、その間に交渉を続けるという意味である。最悪の事態は避けられたとして米関税政策を巡る過度な警戒感が後退し、非鉄金属、鉄鋼など景気敏感株を中心に買いが優勢となった。現在のような状況では、当分の間、日銀は追加利上げをできないとの見立てから、外為市場で円相場が1ドル=146円台の円安ドル高方向に動いたことも株価を支えた。トヨタ自動車、ホンダ、スズキなど自動車株が買われた。日経平均の上げ幅は一時200円を超えた。ただ、8日(約5,600億円)と10日(約9,000億円)は上場投資信託(ETF)の分配金捻出のための売り(大引けで出るのが一般的だが先回りしてザラバで売るトレーダーもいる)が出るため、その分だけ株価の頭を抑えた。
本日現在、日米関税交渉は少しも解決していない。関税交渉を巡る不透明感が長引くと、企業は通期の業績見通しを下方修正する可能性が高い。そのため、関税の影響で景気が悪化するのを防止するため、20日投開票の参院選の後、秋の臨時国会では従来よりも規模が大きい経済政策を打ち出してくるとの読みも株価を押し上げる力となった。相場センチメントは依然として「ブル(強気)」が継続している。ファンダメンタルズでは不安要因が多くあるが、市場はTACO(Tramp Always Chikens Out)トレードを続けている。
参院選では自民・公明の与党が議席を減らすとの見方が増えており、もしそうなれば、財政拡張を唱える野党の影響力が強まる。それを見越して、財政悪化懸念から30年債が売られ、利回りが3.090%へ上昇している。逆に新発5年債(178回債)は応札が堅調で価格が上がり、利回りは0.960%へ低下した。その結果、利回り曲線(イールド・カーブ)はより急傾斜となる「ツイスト・スティープニング」となった。
日経平均の日足チャートを見ると、陽線で小幅反発したが、7月2日以来横ばい相場が継続しており、方向感がはっきりしない。
33業種中20業種が上げた。上昇率トップ5は、非鉄金属(1位)、精密機器(2位)、ガラス・土石(3位)、鉱業(4位)、海運(5位)となった。
ページの先頭へ
ブログトップへ
PC版へ